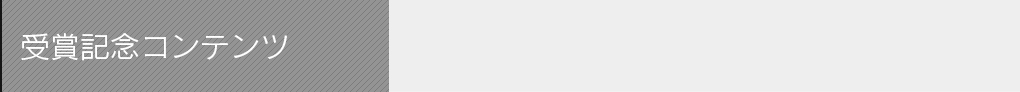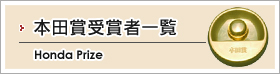※受賞者・ご来賓の所属・役職・プロフィール内容は受賞当時のものです。
2022年本田賞 受賞記念座談会
座談会出席者

当財団評議員
東京大学名誉教授
国際基督教大学名誉教授

東京大学大学院工学系研究科
物理工学専攻 教授
国立研究開発法人理化学研究所 香取量子計測研究室
主任研究員
光量子工学研究センター 時空間エンジニアリング研究チーム
チームリーダー
国立研究開発法人科学技術振興機構 未来社会創造事業
プログラムマネージャー
基礎研究と技術開発が重なる時代
村上: 香取先生のご研究の重要なキーワードが、「Curiosity driven:キュリオシティードリブン(好奇心による駆動)」です。これまでは、基礎科学の世界はCuriosity-drivenであるのに対し、工学系の研究は「Mission oriented:ミッションオリエンテッド(明確な目標を定め、効率的に目標達成に向かう)」として、2つを切り分けてきました。ところが、今の時代はまさにその基礎研究と、それを社会のために応用する技術開発がほぼ重なってきています。
ある研究者は研究の在り方をMode-1とMode-2に分けました。Mode-1は、科学トピックスに牽引者となるような主たる研究者がいて、同じ領域の助手やポスドク、大学院生という階層構造の中で研究を進めていくものです。Mode-2は、いろいろなジャンルの研究者が平面上に網の目のようにたくさん集まり、1つの目標に向かって自分たちの能力と技術とを出し合います。どちらかというと基礎研究は前者、ミッションオリエンテッドは後者の網の目スタイル的ですが、今はこの区別も難しいでしょう。
そんな中で、ご研究を光格子時計に絞られたのは、そのテーマに熱情を注ぐだけの魅力があったのでしょうね。
香取: まず良い研究トピックスに巡り会う幸運に恵まれ、その研究トピックスを自ら発展させる方向を次から次へと見いだせたことがまた幸運でした。私も光格子時計を始めた頃は、他の人々が手がけるようになったら他の研究をやろうと思っていたのです。ところが次から次へとやりたいことが出てきて手放せなくなりました。

誰もやらない研究に取り組むリスク
村上: 「レフェリーバイアス」という言葉があります。ある研究ジャンルのコミュニティがどちらの方向を向くか、例えばジャーナルのレフェリー*が決めてしまう。文字どおり誰もやらないテーマを、研究コミュニティーに論文として投稿することはリスキーではなかったのでしょうか。
* 学術誌の査読者
香取: 誰もやらないことを国際会議でプレゼンテーションしても、最初は会場のごく僅かな人しか何を言っているか分からないものです。私も新しい話を聞くと、その場で意味を全部理解するのは難しくて、繰り返し講演を聞くか、あるいは聞いた後にいろいろな人とディスカッションをしてだんだん分かってきます。
光格子時計にもやはりそういうプロセスがあって、最初に発表したとき、会議の後で議論して「ここのところが分かりにくかった」と聞くと、次のプレゼンテーションでは分かりやすく説明しようとします。そういうインタラクションがあって、やっとコミュニティーがその方向を理解し始めるようになりました。
最初の論文を書いたときも学術誌『Physical Review Letters(フィジカルレビューレター)』のレフェリーから厳しい意見がありました。例えば「おまえの論文は自己引用が多過ぎる」と。自己引用が多過ぎるといっても、その道をつくってきたのは自分ですし。
村上: ほかにいないですからね。
香取: 今も手ごわいレフェリーとして思い出します。次に最初の実験結果を『Nature』に出したときはとても好意的で、1週間ぐらいで掲載が決まりました。担当のエディターがこの研究は大事だと考えると、その価値の分かるレフェリーに回してディシジョンを急ぐので、その流れに乗ったのだと思います。
そのときはレフェリーがとてもいいレビューをしてくれました。「18桁の精度の時計を作るというが、どこで実験をするのか。普通の光学定盤の上で実験をしようとしても、熱膨張でできないはず」と、当時の我々がまだそこまで考えていなかった5年、10年先を見据えるようなコメントをくれました。
村上: それはうれしいお話を伺いました。
原点は「競争しない研究」をすること
香取: 科学コミュニティーは、フレンドリーにできているのだと思います。それがフレンドリーではなくなるのが、同じターゲットに向かった競争が激しいときです。ジャーナルのエディターがレビュアーと研究者とのやりとりを公平に判断するのが難しくなるか らです。光格子時計の研究は当時誰も本気でやる人がいなかっ たので、科学者は「その面白さを見てみたい」とレビュアーを引き 受けてくれた。競争のないところで始めたのはよかったのかもし れません。
村上: 若い研究者に聞いてもらいたいお言葉ですね。あまり競 争的な現場に身をさらすと人間も悪くなります。
香取: 研究のトピックスを探すとき、最初に考えたのが、「競争し ない研究をしたい。しかも面白くて自分たちで楽しめる研究をし たい」ということです。それが原点でした。 ただし、役に立たない研究ではいけない。「今基礎研究をする のであれば、20年後にはそれが社会に役立つ芽を出しているべ きであろう」と思っていましたし、年齢を重ねるにつれてその意識 が高まってきました。大御所の研究者たちが居並ぶ国際会議で 何か大胆なことを言いたい若手だったところから、20年して社会 還元につながるところまで研究が進んだのが、何よりよかったと 思います。
村上: 今は一般の科研費でさえ「社会にどのように役に立つの か」と早い段階で書かなければいけないようになっています。あ れはちょっとしんどいのでは。
香取: ドクターを取ったばかりの30代の研究者は自由に研究す るのがいい。一方で、歳を重ねたら何か社会に役立つこと、あ るいはその先の研究というのを狙っていくべきだと思います。
村上: 確かに、研究者は自分の研究が社会に与える影響を、良 い方も悪い方も考えなければいけない時代です。ただ、あまりに 若い人たちに社会的利益を意識した研究を強いると、本当の意 味でのCuriosity-drivenな研究を阻害するおそれもありそうです。 光格子時計は、研究成果を応用して実際に社会に役立てよう とする人たちが出てきているようですね。
香取: 光格子時計では相対論的に時空の新しいセンシングがで きるので、それをどうやって使おうかを考えています。GNSSの 測位法に対して光格子時計の測位が優位性を発揮するのはどん な場面か、若い研究者と議論しているところです。